寝不足の素
(YamaMori 読書控え)
「晴子情歌」 高村 薫著
昨年(2014年)末から年初にかけて怒涛の勢いで読んだ。
ぶっとんだ。恐れ入った。参りました。感動しました。
ミステリー作家っぽいこの著者がどうやらミステリーではない、なにやら読みにくそうな大きな(ぶ厚い)、難しそうな、つまり読みにくそうな本を出していたことは知っていたが、なかなか棚から取り出そうとはしなかった。要するに尻込みしていたのだ。ネットでも同じような話を多く見かけて安心したが、いつかは読まねばなるまいと思っていた。
読み始めたら一気に引き込まれた。主人公の聡明さと逞しさが魅力で、数々の苦難をまるで他人事のように冷静に分析し対処していく。まあこれは小説だから客観的に書かないと話にならないが、息子への手紙という文体がまた読みやすくて感情移入しやすい。
それでも一般的なレベルで言うと読みにくい部類に入ると思うが、こちらとてジョン・ル・カレなんかで読書力を鍛えてあるのでなんでもない。むしろ読み応え十分の満足感をたっぷり味わいながら読み進めることができた。怒涛の上・下巻である。
前半の山場は戦前の北海道で大いに栄えた鰊(にしん)漁の描写で感動すら覚えた。
後半は打って変わっておどろおどろしい人間模様が描かれる。その登場人物の多さに辟易しつつも、付録の家系図を片手になんとかついていくのである。知人はこれをみただけで読みたくないと言ったが、こうした大勢の人間模様を言葉を駆使して描き切った著者の筆力こそが、本書の真骨頂なのである。内容よりも言葉の力を感じることが大切なのである。
読後の衝撃があまりに大きかったので、すぐに再読した。おかげで家系図はほとんど頭に入った。というか1度や2度では人間関係がわからないのだ。
さらに登場人物の年代表も独自に作ってみた。時と場所があちこちにすっ飛ぶので、そのくらいしないと整理がつかない。
さらにこの物語には続きがあって、「新・リア王」という本がそれである。
さらにさらにまだ先があって、「太陽を曳く馬」という本があって全3部作といわれている。
今年、それらも全部読んだ。圧巻だった。ラストシーンを読みながら泣いたね。晴子と息子と孫の過酷な人生を振り返りながら、最後に戻るのはあの七里長浜の砂と雪と風と雲しかない茫漠とした灰色の風景。映画にしたらすばらしいラストシーンになるでしょう。
現代小説の最高峰ではないか。その凄さを表現するすべを僕は持たないが、まあ読んでみなされ。
いつか真冬の七里長浜に行かなくちゃ。
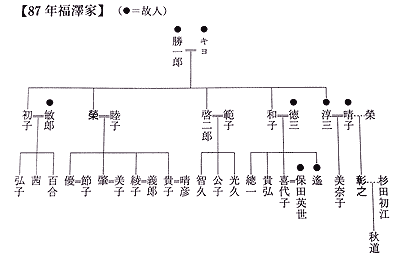
(2015/6/17)
犬の力
ドン・ウィンズロウ 著 角川文庫
メキシコとアメリカの麻薬戦争を30年の長きにわたる戦いを描いた衝撃作。
犬の力とは意訳すれば犬畜生とでもいう意味か。とにかく麻薬マフィアが繰り広げるすさまじい抗争と、それに対抗するアメリカの取締官たちの壮絶な戦い。
しかしその戦いの真実を知れば知るほど実態は茶番としかいいようのないものに見えてくる。そこに需要がある限り麻薬の供給は絶えることはない。
また麻薬戦争の名の下で遂行される対共産主義との戦いをアメリカはベトナムで懲りずにまだやっているのである。というか、あり余る軍事力の供給が過剰となり、今では自ら需要をつくりださなければ生きていけない軍産複合体という巨大な悪魔に支配されている国家の実態。あな恐ろしや。
いっそのこと麻薬の輸入を合法化してしまえば麻薬の値段は暴落し、この戦争も終わること確実なのだが。
いやあ久しぶりに興奮する本を読んだ。
(2010.10.31)
アフリカ入門
川田順造(編)新書館
「一元化され硬直した開発思想、(中略)明らかな行きづまりに陥っている開発のあり方を、アフリカの毒を解毒剤として、根本から、生きることの意味にまでさかのぼって問い直すことが、いまこそ必要だと思うのだ...」
毎日新聞の書評に感銘を受けて読んだ本。
内容はアフリカの自然、歴史、民族、文化など多岐にわたるアフリカ学の入門書。
その監修をしたアフリカ研究者の方が序文に書いた上の言葉は、多くの人々に強い印象を与えたらしい
様々な社会的問題を抱えながらも、人間などそこに生きる小さな動物のひとつにすぎないという人間本来の姿を思い起こさせるアフリカの大地に立つとき、高度な産業文明と経済至上主義の下であくせく働きながら、幸せを追い求めて苦悩する多くの日本人にとって、なにもアフリカに限った事ではないが、人類創生の地といういわば人類の故郷の意味を込めて、アフリカとそこに生きる人々の生活を顧みることは、決して無駄ではないと言うのである。
悲惨なニュースを聞くたびに日本人は、そして世界はどうかしていると感じる今こそ、あえてアフリカの毒に触れてみるのも、一つの有効な救済策なのかもしれない。
しかしながら絶えることのない紛争と貧困を目の当たりにしては、そう悠長なことも言ってられないような気もするが。
サバンナの手帳
本書はアフリカに毒にどっぷり浸かった日本の文化人類学者がニジェール川周辺の歴史と文化を時空を超えて旅する紀行文。
かつて欧米人から暗黒大陸なんて呼ばれていた時代もあったけど、当たり前だがアフリカにも独自の歴史があり文化がある。単に我々の教科書に載ってないだけだ。
サファリで野生動物を見るだけじゃアフリカは理解できない。
川田順造 著
となり町戦争 (三崎亜記 著)
題名からして変な感じの話題になった本を書棚で見つけたので読む。しかし予想以上に変な内容であった。
地方のある町がとなりの町と戦争をおっぱじめる、というわけのわからん内容で興味をそそるが、そりゃいったいどんな戦争なのかとい う疑問はいくら読 んでも解けない。
そしてその疑問はこの小説の主人公にとっても同じ疑問のまま、読者とともに話は進む。
と、そこが作者の意図したところのようで、町の広報に小さく掲載される戦死者の数だけが戦争の事実を伝えるだけで、今日のようにマスコミが大々的に報じる戦場の生々しい情報は一切ない。
さらに、妙にリアルなのがこの戦争を町の公共事業として粛々と遂行している町役場の業務内容である。しかしそれも極めて一面的な部分、つまり主人公がこの戦争と関わりあう部分のみが描写されるだけで、その全体像は一切見えない。
いったい作者はこの小説で何を言いたいのか。読者は嫌でも考え込まずにはいられない。
思うに、作品の中で繰り返し書かれる戦争のリアルさをどう実感するかという点にこの作品のテーマがあるようだが、要するに平和ボケし た日本人にとって海 の向こうの戦争が決してリアルに感じられないことへの違和感を描きたかったのか。
その中で妙にリアリティがある行政の対応はなんなのかと思ったら、要するに公務員でもある著者の日常業務だったのね。うがった見方をすれば、リアリティを出せる部分はそれだけってことか。
ネットで書評を拾い読みしたけど、やはり賛否両論ですな。批評家受けする部分も確かにあるような気もするけど、とにかく主人公の言動からなにからリアリティがまったくないのでほとんど感情移入できす、僕には面白くなかっ た。
あとで知ったがこれ映画化されたんだと。見ネーよこんなの。
(2008/4/27)